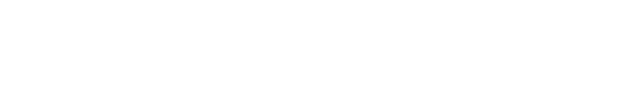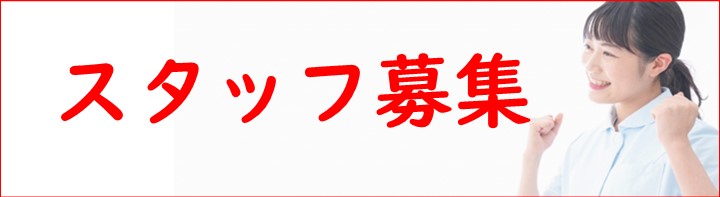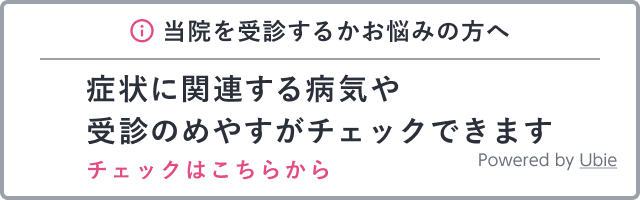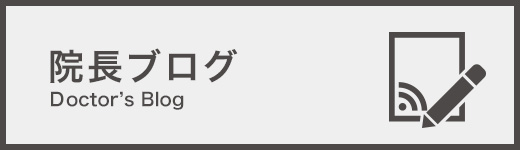自己免疫性胃炎とは?
私たちの体は外からの病気や感染から守るために免疫システムという仕組みを持っています。
免疫システムは、ウイルスや細菌などの外部からの敵を見つけて戦う役割を担っています。
しかし、時には免疫システムが誤って自分自身の体の一部を攻撃してしまうことがあります。
これを「自己免疫」と呼びます。今回は、その一例である「自己免疫性胃炎」について説明します。
自己免疫性胃炎って何?
自己免疫性胃炎(じこめんえきせい いえん)は、胃の中の細胞が自分の免疫システムによって攻撃されてしまう病気です。
通常、免疫システムはウイルスや細菌などの異物に対して反応しますが、自己免疫性胃炎では、免疫システムが誤って胃の細胞を敵だと認識し、攻撃します。
この結果、胃の内側に炎症が起きます。
どうして胃の細胞が攻撃されるのか?
自己免疫性胃炎の原因は、まだ完全には解明されていませんが、年齢や遺伝的な要因が関係していると考えられています。
自己免疫性胃炎の病態は、「胃の内壁にある細胞に対して免疫システムが過剰に反応する」ということです。
胃の内壁=胃粘膜にある細胞は、胃酸やペプシノゲンといった栄養の消化吸収に必要な成分を分泌する役割を持っています。免疫システムがこれを長時間攻撃し続けることで、胃粘膜の細胞が破壊されると胃酸の分泌や特定の栄養素の吸収がうまくいかなくなります。
その結果、病気が進行すると貧血になったり痺れや舌の炎症を起したりします。
自己免疫性胃炎の症状
自己免疫性胃炎は初期に自覚症状は乏しく、長期にわたり無症状のまま徐々に進行していきます。
進行後に出現する自覚症状も特徴が少なく症状や簡単な診察だけでは自己免疫性胃炎の診断をすることはできません。
健康診断で「貧血」や、ペプシノゲン検査の異常を指摘されることが診断のきっかけになります。
自己免疫性胃炎が進行した際の症状には以下のようなものがあります。
貧血

自己免疫性胃炎が長期間続くと、胃の粘膜にある壁細胞という細胞が傷つきます。
壁細胞は胃酸とビタミンB12を吸収するための内因子と呼ばれる物質を作っています。
胃酸が少なくなると鉄分を吸収しにくくなります。そのため鉄分不足による貧血(鉄欠乏性貧血)になります。
また、内因子が不足するとビタミンB12の吸収が悪くなります。ビタミンB12が身体の中に足りなくなってくると巨赤芽球性貧血というタイプの貧血が起きてきます。
舌炎(Hunter舌炎)
「舌が赤くてツルツルになった」「辛い物を食べたわけでもないのにヒリヒリする」—これはB12不足による舌炎の典型的なサインです。
味覚が落ちることもあります。
神経症状(神経障害)
ビタミンB12は神経の健康にも大事な栄養素。足の裏がしびれる、感覚が鈍い、まっすぐ歩きにくい、といったしびれやふらつきが出ることがあります。

排尿や排便の障害がでることもあります。
精神・認知機能への影響
B12不足は脳にも影響します。
なんとなく元気が出ない、気持ちが落ち込みやすい、最近物忘れが増えた…といったメンタルや記憶の異常が病気に気づくサインになることもあります。
消化器症状
自己免疫性胃炎は、病気の中心が胃にあるにもかかわらず、胃腸の不調を感じることはまれです。
一部の患者さんでは次のような消化器症状を自覚することがあります。
胃の痛み
自己免疫性胃炎の症状のひとつが胃の痛みです。特に食後に胃が痛くなることがあります。
吐き気や嘔吐
胃の中が炎症を起こしているため、気持ちが悪くなったり、吐き気を感じることがあります。
ひどくなると嘔吐してしまうこともあります。
胃もたれや膨満感
食べ過ぎたわけではないのに、胃の中が重く感じたり、膨れた感じがすることがあります。これも胃の炎症の一環として現れる症状です。
食欲不振
胃の炎症が続くと、食欲がなくなることがあります。食べ物を食べた後に胃が不快に感じることが多いため、食事が楽しめなくなってしまう方がいます。
どんな人がかかりやすいの?
自己免疫性胃炎は誰でもかかる可能性がありますが、特に次のような人がかかりやすいと言われています。
また、欧米での有病率約2%に比べて日本での有病率は0.89~0.9%とやや少なめの傾向がありますが、調査方法や世代、ヘリコバクターピロリ感染率の影響があるため単純な比較はできないようです。
年齢が高い人
自己免疫性胃炎は、特に中年以降の人に多く見られます。
診断時の平均年齢は50~60歳代で、悪性貧血がきっかけで診断される場合は60歳以降が多いです。
他の自己免疫性疾患を合併している場合は、30~40歳代でも自己免疫性胃炎と診断される可能性があります。
免疫システムが弱くなったり、バランスが崩れることが原因と考えられています。
女性
女性の方が男性よりも自己免疫性胃炎になりやすいというデータがあります。
多くの疫学研究で、男女比はおおむね 女性:男性 = 2〜3:1 程度です。
女性ホルモンの影響が関係しているのかもしれません。
家族に自己免疫疾患の人がいる
自己免疫性胃炎は遺伝的な要因が関係している可能性もあります。
家族に自己免疫疾患の人がいると、かかりやすくなることがあります。例えば、橋本病や1型糖尿病、Addison病などです。
自己免疫性胃炎が遺伝したり家族内で多発しやすかったりはしないとされていますが、「免疫がかかわる病気に罹りやすい体質が遺伝する」と考えられています。
他の自己免疫疾患を持っている人
糖尿病や甲状腺の病気、関節リウマチなどの自己免疫疾患を持っている人は、自己免疫性胃炎にかかるリスクが高いとされています。
どうやって診断するの?
自己免疫性胃炎を診断するには、いくつかの方法があります。
まずは、病院で医師が症状を詳しく聞き、身体検査を行います。その後、以下のような検査が行われることがあります。
血液検査
血液中の成分を調べることで、自己免疫性胃炎が疑われるかどうかを確認します。
例えば、胃の細胞を攻撃している免疫物質がないかを調べたり、炎症が長く続いて胃粘膜が弱ったことを示す検査異常を調べたりします。
自己抗体検査
抗壁細胞抗体(anti-parietal cell antibody)
最も特徴的な検査項目。感度は比較的高いが特異度はやや低い。
健常者でも低力価で陽性になることがあり、加齢でも偽陽性がでやすい。
抗内因子抗体(anti-intrinsic factor antibody)
特異度が高く、悪性貧血の診断確定に有用。
感度は低いため、陰性でもAIGは否定できない。
胃酸分泌・胃粘膜関連マーカー
血清ガストリン
自己免疫性胃炎では壁細胞が破壊されるため胃酸が少なくなります。
すると胃幽門前庭部にある G細胞から胃酸分泌を促すホルモンの「ガストリン」が多く分泌されます。
ペプシノゲン(PG)
ペプシノゲンは胃体部萎縮のマーカー。
自己免疫性胃炎では胃粘膜の萎縮が起こり、PGⅠ低値、PGⅠ/Ⅱ比の低下が見られます。
吸収障害に関連する所見
ビタミンB12低値
壁細胞でつくられる内因子が欠乏するためビタミンB12の吸収障害 が起こります。
ビタミンB12はDNA合成に不可欠な栄養素なので、これが不足すると新しい赤血球を作るためのDNA合成が滞ってしまします。その結果、巨赤芽球性貧血というタイプの貧血が引き起こされます。
鉄欠乏
胃粘膜が弱り胃酸が不足すると、鉄イオン(Fe³⁺ → Fe²⁺)変換障害で鉄分が吸収されにくくなります。
その結果、血清鉄やフェリチンが低値となります。
内視鏡検査(胃カメラ)
胃の中を内視鏡を使用して直接観察します。
自己免疫性胃炎では、「萎縮」という粘膜の瘦せ衰えが見られます。
ヘリコバクターピロリ菌感染でも萎縮が見られますが、ヘリコバクターピロリ菌による萎縮が胃の出口付近(前庭部)から広がるのに対し、自己免疫性胃炎の萎縮は胃の真ん中あたり(胃体部)が中心です。
萎縮が進むと本来の胃のシワがなくなって平らなツルツルな胃に見えます。
ポリープのような粘膜の盛り上がりが複数みられることもあります。
組織検査(生検)
内視鏡で見た胃の組織を少し取り、細胞の状態を顕微鏡で調べることがあります。
胃酸やペプシノゲンの分泌を担う壁細胞や主細胞が炎症でこわされて、胃粘膜の構成がおかしくなっていること、足りなくなった胃酸分泌を促すためにガストリンを分泌するG細胞やガストリンの刺激を受けてヒスタミンを産生するECL細胞が多くなることが主な顕微鏡の所見です。
①正常胃底腺にある壁細胞(AIG の主役細胞)や主細胞の変性・減少・消失
②胃腺部腺管が頸粘液細胞ないし幽門腺細胞からなる化生粘液細胞で置換
③化生腺管内に ECL 細胞過形成
④前庭部幽門腺粘膜にはガストリン細胞過形成
どんな治療が必要?
自己免疫性胃炎に対する根本的な治療はありません。このため症状を和らげ、不足する栄養素を補う治療が基本となります。
治療法は個々の患者さんの状態によって異なりますが、一般的には以下のような治療が行われます。
支持療法
自己免疫性胃炎によって消化器症状が現れることは少ないですが、胃痛や膨満感、食欲不振に対して症状を和らげる薬物治療が行われます。
ビタミンB12の補充
自己免疫性胃炎が長引くと、ビタミンB12の吸収が悪くなります。
ビタミンB12が不足すると、貧血や神経障害、精神障害が起こるため、補充することが必要です。
内服薬と注射による治療があります。
鉄補充
胃酸分泌による鉄欠乏性貧血は比較的早期から出現します。
鉄欠乏はビタミンB12欠乏より早いタイミングで出ることが多いです。
食事療法
胃の不快な症状を和らげるためには、食事の改善も大切です。
脂っこい食べ物や刺激物を避け、消化に優しい食べ物を摂るように心がけると良いでしょう。
定期的な検診(発癌リスクへの対応)
自己免疫性胃炎は、胃体部胃癌や胃カルチノイド腫瘍のリスクが高いです。
1~2年ごと、胃内視鏡検査を受けましょう。
症状がなくても、定期的な医師の診察と検査を続けることが推奨されます。
まとめ
自己免疫性胃炎は、免疫システムが胃の細胞を攻撃して炎症を引き起こす病気です。
主な症状は、貧血による易疲労、息切れ、倦怠感と神経障害によるしびれ。
まれに胃の痛みや食欲不振、吐き気などの消化器症状あり。
早期には症状を伴わないことがほとんど。
治療は、不足する栄養素の補充が中心。医師の指導に従って治療を進めましょう。
自己免疫性胃炎の原因はまだ完全には分かっていませんが、家族歴や年齢、性別などの要因が関係しているとされています。

消化器病専門医・消化器内視鏡専門医
肝臓専門医・総合内科専門医
本城信吾 院長
南北線南平岸駅から徒歩6分、リードタウン平岸ベースにある消化器内科
ほんじょう内科
北海道札幌市豊平区平岸1条12丁目1番30号 メディカルスクエア南平岸2F
TEL:011-595-8261