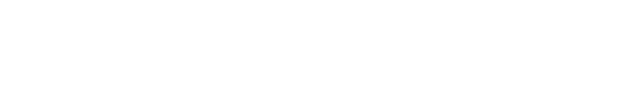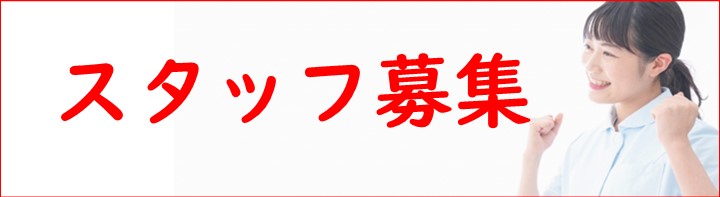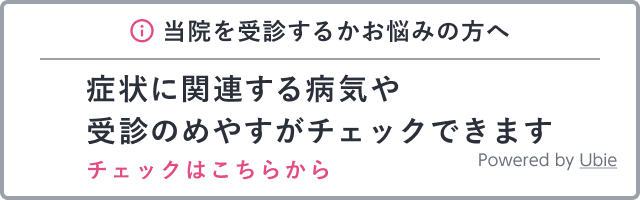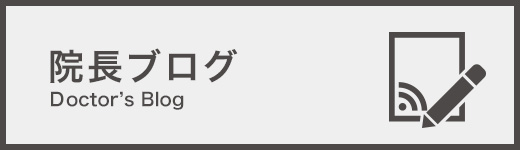大腸鋸歯状病変ってなに?―診断・治療のいまをやさしく解説!
大腸がん、第3の発がんルート “serrated pathway”
みなさん、「大腸がんって、腺腫(adenoma)からできるんでしょ?」って思っていませんか?
たしかに、昔から「腺腫→がん」っていう王道ルート(いわゆるadenoma-carcinoma sequence)は有名ですよね。大腸がんの60~70%は腺腫性ポリープから発生しています。
もう一つは、de novo pathwayと言われている正常粘膜からいきなり癌が発生する発がんルートです。0-Ⅱc型のような陥凹型病変が多く微小な病変でも浸潤傾向が強いとされています。
そして第3のルート、「鋸歯状経路(serrated pathway)」。このルートに関わるのが、「大腸鋸歯状病変(serrated colorectal lesions)」と呼ばれるポリープたちです。
中でもSSL(sessile serrated lesion)っていうタイプが、大腸がん(特に右側結腸がん)の“黒幕”的存在として注目されています。
1. SSLってどんなポリープ?―鋸歯状病変の分類と発がんの仕組み
1-1. 鋸歯状病変って、どんな仲間がいるの?
WHOの最新分類(2019年)では、鋸歯状病変は以下のように分けられています。
- HP(hyperplastic polyp):昔からある良性の過形成ポリープ。主に左側結腸に多い。発がんリスクは極めて低い。
- SSL(sessile serrated lesion):今回の主役。右側に多い、がんの予備軍。
- SSLD(SSL with dysplasia):SSLに異型(dysplasia)が加わった、より危ないやつ。
- TSA(traditional serrated adenoma):左側に多く、これもがんのタネになる。
SSLは以前SSA/P(鋸歯状腺腫)と呼んでいたものとほぼ同じ。
1-2. がんになる流れ:SSLが歩む“鋸歯状ルート”
SSLは、普通の腺腫と違ってこんな発がんメカニズムの特徴を持っています
- BRAF遺伝子の変異(よく出てくるのがV600E型)
- CpGアイランドメチル化表現型(CIMP-high)
- MLH1のメチル化 → MSI-highのがんへ進展
このルートを通ってがんになるケースは、大腸がん全体の15~30%とも言われています。意外と多いですよね。
2. 内視鏡でどう見える?―SSLの“顔つき”を見抜こう
2-1. 内視鏡通常観察で見たときのポイント
SSLを見つけるには、以下の特徴をチェックしましょう
通常観察でのSSLの特徴
- 10mm以上のサイズ
- 右側結腸(盲腸~上行結腸)にできやすい
- 平坦な形(0-IIa)
- 粘液がたっぷりのってることが多い
- 境界がぼやけてて、雲みたいな見た目(cloud-like)
個人的には、「白っぽい粘液がくっついて取れにくい」のが、SSLを見つける一番のきっかけだと思っています。
2-2. IEE・拡大観察ではここを見る!
NBI/BLI(狭帯域光観察)や色素拡大でSSLを見ると…
II型pitが開いたような“II-O型”(開Ⅱ型)
腺管の開口部が丸く広がって見える
血管も、lacy vessel(HPに多い)とは違って「太く枝分かれした血管」( thick and branched bessel )が目立ちます
ちなみに、病理の「鋸歯状」っていうのは腺管の深いところの形で、内視鏡では“ノコギリ”には見えません。だから、表面の構造や周囲の粘液、色味なんかを総合して判断する必要があります。
3. HPとSSLの見分け方
「ちっちゃいし、HPじゃない?」って油断してると、実はSSLだった…なんてことも。
HPとSSLの違いをざっくり整理するとこんな感じ
| 比較項目 | SSLに多い | HPに多い |
|---|---|---|
| サイズ | 6mm以上 | 5mm未満 |
| 場所 | 右側結腸 | 左側結腸・直腸 |
| 境界 | 不明瞭 | 明瞭 |
| 粘液付着 | あり | なし |
| pit pattern | Ⅱ-O型など | Ⅱ型(star-like) |
| 血管 | 太く枝分かれ | lacy vessel |
とくに右側で10mm以上、粘液ついてて、ぼんやり見えるやつは、ほぼSSLと疑ってOK。
4. 切る?切らない?―SSLの治療適応と手技選び
4-1. ガイドライン的には…
将来の大腸がんを予防するためには、どんな鋸歯状病変を切除するのがいいのでしょうか?
『大腸ポリープ診療ガイドライン2020』内視鏡サーベイランスのCQ14ではこう書かれてます
- TSA、SSLD、および10mm以上のSSLは切除を推奨
- HP(特に左側・5mm未満)は経過観察でもOK
でも実際は、右側のSSLっぽいポリープは、5mm前後の場合でも「将来の大腸がんリスクを減らすため」積極的に切っちゃうことが多くなってきてます。というのも、コールドスネアポリペクトミー(CSP)の普及で簡便で安全に小さい病変を切除できるようになり、少しでも発がんの不安がある病変はどんどん切除して積極的に大腸がんを予防しようという考え方が受け入れられるようになってきています。
ただし、5mm前後の小さいSSLを治療するかどうかは医師や医療施設の間で方針や考え方の違いがあり、専門医の間でも一定の見解は得られていないようです。
4-2. SSLの切除法のバリエーション
| ポリープのサイズ | 推奨される切除法 |
|---|---|
| ~5mm | Cold forceps または CSP |
| 6〜9mm | CSP、分割cold EMR |
| 10〜20mm | EMR、UEMR(できれば一括) |
| >20mm | EMRまたはESD(異型疑いあればESD) |
CSP(cold snare polypectomy):小さいSSLに最適。安全で手軽。
UEMR(underwater EMR):局注不要で比較的大きな病変も一括切除可能。
ESD:SSLDや早期がん疑いなら一括でしっかり取れるESD一択。
4-3. SSL with dysplasiaを疑うサイン
SSLの中にがん化(異型)が潜んでる場合、こんな所見が出てくることがあります
- 発赤、表面のざらつき、陥凹
- ⅢL型やVI型のpit pattern
- 結節性の隆起や表面の盛り上がり
これらの所見があれば、ESDで一括切除がベストチョイスですね。
5. 鋸歯状経路(serrated pathway)ってなんだ?
SSLやTSAは、腺腫とは違う発がんメカニズムをたどってがんになります。
それぞれの遺伝子変異の特徴やエピジェネティクスについてまとめました。
| 項目 | SSL(serrated pathway) | 腺腫(adenoma-carcinoma sequence) |
|---|---|---|
| 初期変異 | BRAF | APC |
| 進展変異 | SSLではまれ、TSAにKRAS変異多い | KRAS変異、TP53変異 |
| エピジェネティクス | CIMP-high | 少ない |
| MSI | MSI-highまたはMSS | 主にMSS |
| 組織型 | 粘液癌、鋸歯状腺癌 | 管状腺癌など |
とくに SSL with dysplasia からの発癌は進行が早いとされており、発見されたら早めに対処すべきと考えられています。
6. まとめ~SSLを“なんとなく見逃さない”ために
- 右側大腸で10mm以上
- 平坦で粘液がのっている
- 輪郭がぼやけている
- pitが丸く開いてる
- 内部の血管が太く枝分かれしてる
―こんなポリープを見たら、「あ、これSSLかも」と気づけるようしなくてはいけませんね。
SSLは、発見して、切除できれば、それだけで「将来の大腸がんを防げる可能性が高い病変」です。
切るかどうか迷ったら、切る。それがこれからの鋸歯状病変治療のスタンダードになりそうです。

消化器病専門医・消化器内視鏡専門医
肝臓専門医・総合内科専門医
本城信吾 院長
南北線南平岸駅から徒歩6分、リードタウン平岸ベースにある消化器内科
ほんじょう内科
北海道札幌市豊平区平岸1条12丁目1番30号 メディカルスクエア南平岸2F
TEL:011-595-8261